産学官連携ニュース No.02 Web版
発行:2009年9月25日
目次
イノベーションジャパン2009
平成21年9月16日(水)から3日間、日本全国の大学が学内に保有する優れた知財、産業シーズを広く産業界に紹介することを目的に、(独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の主催、文部科学省、経済産業省、内閣府、日経BP社の共催で有楽町の東京国際フォーラムにおいて第6回目となる表記展示会が開かれました。別名を「大学見本市」と称し、国公私立の大学の展示では最先端技術8分野のシーズ展示が352ブース、大学知財本部13ブース、全国のTLO(技術移転機関)が29ブース、大学発ベンチャービジネスが24ブース、独立行政法人や地方自治体の研究機関が19ブース、その他に大学発ベンチャー支援機関、産学連携に取り組む主催者のJST、NEDOが出展しました。新しい試みとしてアジアの大学が10ブース展示されました。また、「大学食の祭典」と題して大学発の食品を製品化した企業が33のブースを構え、1日3回の試食・試飲会が開催され大変好評でした。
ブース展示以外では、注目される新技術やビジネスモデルを研究者が自らプレゼンテーションする「新技術説明会」で216件の発表(発表のみで展示のないもの41件を含む)、著名人の講演を行う「イノベーションジャパン2009フォーラム」などのプログラムで、今年度は主催者発表で41,000人以上の入場者があったわが国最大の大学関係展示会です。
本学量子・物質工学科の 牧 昌次郎 助教の「ホタル生物発光系のモデル化と多色発光標識材料の創製」と、レーザー新世代研究センターの 中村 伸行 准教授の「高温超伝導コイルを用いた新しい小型多価イオン源」の2件をブース展示した他、電気通信大学としては産学官連携センターが組織のご案内と知的財産部門の「UECソフトウェア・リポジトリのご紹介」を展示しました。また、TLOゾーンにはキャンパスクリエイトが出展しました。
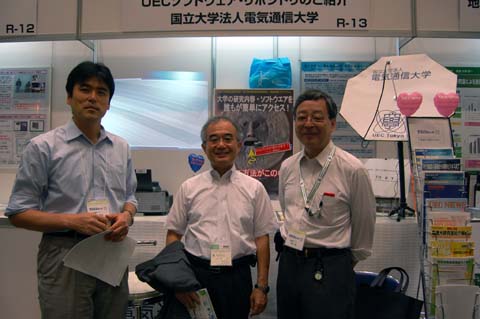
学長と電気通信大学のブース
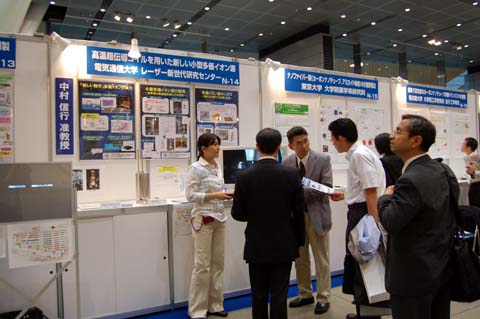
牧助教と中村准教授の展示
第22回国立大学共同研究センター専任教員会議報告
産学官連携センター 准教授 田口 幹
第22回国立大学共同研究センター専任教員会議は、8月27日(木)、28日(金)に、当番校である岩手大学により岩手県花巻温泉千秋閣で開催されました。
今回の会議は、本会議の公式参加者は、55大学74名でした。文部科学省より1名、岩手大学より2名を加えて、全出席者は77名でした。会議規則に基づき本年度当番校の岩手大学 今井 潤准教授を議長に選出した後、幹事会を代表して本年度の幹事長である愛媛大学 入野 和朗 准教授から、今回の専任教員会議の趣旨説明がなされました。今年度は、本来の会議の趣旨に立ち返り、専任教員間での情報交換を最大の目的として、時間をかけて議論をすることとなりました。
分科会のテーマは、昨年と同じ4つに加えて、知的財産に関わる専任教員が増えていることから、分科会Ⅴとして「知的財産の取り扱いやそれを取り巻く環境の変化」として、議論を行うこととしました。
第1日目は、岩手大学 理事(総務・地域連携担当)齋藤 徳美 副学長から開会のご挨拶に続き、全体会として文部科学省研究推進局研究環境・産業連携課 技術移転推進室 岩田 行剛 専門官より、基調講演として「文部科学省における産学官連携推進に関する施策について」と題して、次年度の概算要求を含めた方針などについて、講演頂きました。
その後、「専任教員ミッションの変化・拡大と専任教員会議のあり方」、「産学官連携人材の育成・評価と学内体制の整備」、「地域における産学官連携」、「大学間連携」、「知的財産の取り扱いやそれを取り巻く環境の変化」の5つの分科会に分かれて、よりつっこんだ報告と議論が重ねられました。2時間半を超える議論の後、分科会は終了しました。まだ議論のつきない分科会もありましたが、夕刻からは会場を千秋閣宴会場に移して情報交換会を行い、和やかな雰囲気の中、さらに意見交換を深めて第1日目を終了しました。
第2日目には、再び全体会が開かれ、各分科会コーディネータから、分科会報告が行われ、情報共有が図られました。また、次期幹事および幹事長を選出し、来年度の開催当番校を佐賀大学に決定しました。
今回の会議から、十分な分科会の時間を確保するためと、専任教員間の懇親の時間を十分に取るため、温泉に泊まり込んで、専任教員会議を実施しましたが、非常に好評であったため、次年度以降も今年以上に十分な時間を取って、情報交換ができる専任教員会議の開催を期待することが確認されました。 会議終了後の午後には岩手大学地域連携推進センター、盛岡市産学官連携研究センターの見学会が設定され、会議参加者の内30名ほどが参加しました。施設の見学並びに岩手大学の産学官連携の紹介の後、当日開催されたINS夏季講演会、交流会に参加しました。

岩手山
第1回TOKYO産学公連携合同フォーラム
産学官連携センター 准教授 田口 幹
本フォーラムは、東京都に立地する国公私立大学及び研究機関・東京都中小企業振興公社合計11団体が結集し、東京都区市町村を対象として「安全安心に資する」「地域企業に活用される」等の研究成果や、実施中の産学公連携活動・施策を紹介することを目的に、地域で活躍する区市町村行政機関の方、中小企業振興に尽力されている方に参加いただき、新時代の東京が求める産学公連携方策について、大学・研究機関と自治体で積極的に情報交換し、新しい産学公連携に踏み出すことを目的に開催しました。参加機関は(財)東京都中小企業振興公社、(独)産業技術総合研究所、工学院大学、首都大学東京、中央大学、電気通信大学、東京海洋大学、東京理科大学、日本大学、(学)日本医科大学、明治大学でした。本学では竹内特任教授が「『地域産業振興講座』のご紹介」と題して講演しました。
東京圏の国公私立大学のジョイントによるイベントは初めてのことで参加者は101名を数えました。新聞にも掲載され大きな反響を呼びました。
この試みは東京圏で産学連携に関与する国公私立大学や研究機関のコーディネータが相互の連携を取り、情報を共有することによってお互いのスキルの向上を図ろうという「東京お節介倶楽部」が初のイベントとして企画したもので、今後もこのような試みを企画していく予定です。

ポスター展示

竹内特任教授の講演
お知らせ
産学官連携センター運営委員会
平成21年7月9日(木)、本センター4階研修室において第2回産学官連携センター運営委員会が以下の議題で開催されました。
- 共同研究・受託研究の受入れについて
- 特任教員について
- 電気通信大学発ベンチャー・事業化シーズ創出支援事業の公募について
- センター英文名称について
- その他報告事項
研究開発セミナー(予告)
産学官連携センター主催の第76回研究開発セミナー「非接触ICカードの先端技術」- タッチで変わる私たちの未来社会 -を10月20日(火)14:00~17:40に電気通信大学 産学官連携センター4階研修室で開催します。詳しくは本部門のホームページにあるご案内をご覧ください。参加申込みもできます。
なお、第77回研究開発セミナーは11月17日(火)に「ロボット」をテーマに、第78回研究開発セミナーは12月3日(水)に「太陽電池」をテーマに開催します。
詳しくは約1月前頃から本部門のホームページに掲載しますので、ご参照ください。皆様のご参加をお待ちしております。
対外活動と社会貢献
テクノトランスファーinかわさき2009
平成21年7月8日(水)~10日(金)、川崎の神奈川サイエンスパーク(KSP)において表記展示会が開催され、比企コーディネータと田口准教授が参加しました。
首都大学東京産学公交流会
平成21年7月24日(金)、首都大学東京南大沢キャンパスにおいて表記交流会があり、比企コーディネータ、小島コーディネータ、田口准教授が参加しました。ポスター発表と研究室ツアーなど盛りだくさんの交流会でした。
シナジースキーム事業準備会
平成21年7月29日(水)、調布市商工会において本年度のシナジースキーム事業の準備会が開催され、田口准教授が委員として参加しました。本年度は「ものづくり企業への支援」として中小企業の技術者向けの「ものづくり支援セミナー」を開催すること、電気通信大学の教員が講師として協力することが決まりました。10月より16回の講座を開くことになりました。
第6回産学官連携学会大会
平成21年8月17日(月)、19日(火)の両日、福井市商工会議所を会場として表記大会が開催されました。田口准教授が参加し、セッションの司会と口頭発表を行いました。なお、本大会は5月に開催の予定でしたが、新型インフルエンザの影響で延期されていたものです。
コラボ産学官学長フォーラム
平成21年9月10日(木)、コラボ産学官プラザ in Tokyo において有限責任中間法人コラボ産学官の発足1周年を記念して記念式典とコラボ産学官加盟の9大学の学長によるフォーラムが開催され、本学の梶谷学長も参加しました。
